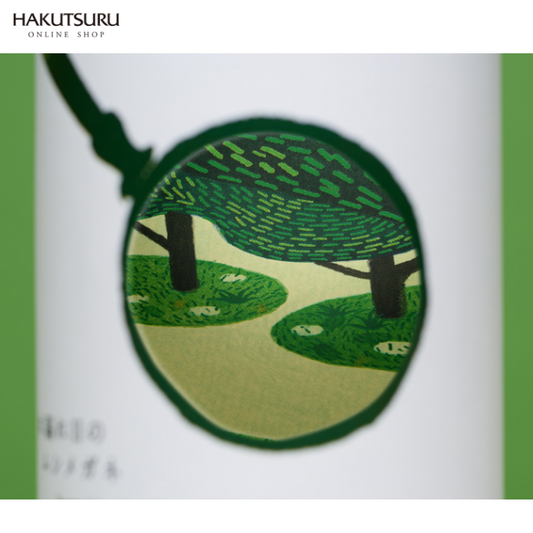「酒造」の世界は奥が深い!「酒蔵」との違いも解説!
Share
お酒を造ることを「酒造」と言いますが、「酒蔵」と混同されることも少なくありません。
この記事では、「酒造」という言葉の意味や「酒蔵」との違いなどの基本知識を解説した上で、酒造にまつわる様々な情報をお届けします。
酒造について知ることで、日本酒をより深く味わうことができるようになるでしょう。
- 白鶴酒造オンライン編集部
白鶴酒造が運営する「白鶴オンラインショップ」の編集部。
メンバーは研究開発と商品開発を経験した2名で構成。
開発担当時に得た知識を活かして、日本酒のちょっとした知識や楽しみ方、季節にまつわる情報をご紹介します。
「日本酒に興味はあるけれど、なんだか難しい~!」という声を少しでもなくすべく、分かりやすい情報を発信していきます!
「酒造」とは?

「酒造」という言葉を耳にすることはありますが、その意味について深く考える機会は少ないのではないでしょうか。
まずは、「酒造」という言葉の意味や混同されやすい「酒蔵」との違いなど、「酒造」についての基本知識を解説します。
「酒造」の意味は?読み方や使い方も解説

「酒造」は「酒造り」という意味を持つ言葉で、「しゅぞう」と読みます。
「酒造」を使った言葉には、酒造りを生業とする人を意味する「酒造家」、お酒を醸造する場所を表す「酒造場」、酒造りをする上で必要な免許である「酒造免許」などがあります。
また、お酒の製造元を指して「酒造メーカー」という言葉が使われることがありますが、「酒造」も「メーカー」も「造り」という意味を含んだ重複表現であるため、お酒の製造元を表す場合には「酒造会社」などと表現した方が無難です。
「酒造」と「酒蔵」の違いは?

「酒造」と「酒蔵」は混同されやすく、誤って使われることがありますが、それぞれ意味が異なります。
先述のとおり、「酒造」は「酒造り」を意味し、お酒を造る行為や仕事自体を表しています。
それに対して、「酒蔵」はお酒を醸造・貯蔵する蔵を意味する言葉です。
「お酒を造る場所」という点では「酒造場」と同じような意味合いです。
読み方は「さかぐら」で、「しゅぞう」とは読まないため注意が必要です。
「酒」と「蔵」をそれぞれ音読みにすると「しゅ」「ぞう」と読めてしまうため、「酒造」と混同されやすいと考えられます。
造り酒屋とは?

「酒造」に関連する言葉として「造り酒屋」があります。
「造り酒屋」とは、お酒を製造し販売する会社や職業のことで、多くの造り酒屋は小売り用の店舗を併設しています。
お酒の製造・貯蔵から販売までを一貫して担っており、「◯◯酒造」という名称の造り酒屋も多くあります。
多くの昔ながらの造り酒屋では、軒先に吊るされる杉玉がシンボルとなっています。
杉玉には、酒の神様への感謝や祈りを捧げる意味合いがあります。
新酒ができたという目印に新緑の杉玉が掲げられ、季節の変化とともに薄緑を経て茶色く変化していく杉玉の色が、新酒の熟成具合を表しているとも言われています。
酒造には免許や資格が必要?
お酒を造るには酒造免許が必要で、免許を持たない者がお酒を造ることは酒税法で禁止されています。
また、酒造免許とは異なり必須資格ではありませんが、酒造りに関する技術や知識の裏付けとなる酒造技能士という国家資格も存在します。
では酒造の免許や資格とはどのようなものなのでしょうか。
この章では、酒造に関する免許や資格について解説します。
酒造免許とは?

お酒を造るには酒類製造免許が必須です。
酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに製造免許を受ける必要があります。
この免許を持たない者がアルコール分1%を超えるお酒を造ることは違法で、処罰の対象になります。
免許を得るには、設備や最低製造量など様々な要件をすべてクリアする必要があり、一定の条件を満たした者だけが酒造りを許されます。
酒造技能士の資格とは?

酒造りに関連して、酒造技能士という資格があります。
酒造技能士の資格は酒造りをする上で必須の資格ではありませんが、酒造りに関わる人の技術と有識を証明してくれる国家資格です。
酒造りに関する資格の中では唯一の公的資格で、学科試験と実技試験に合格した者がこの資格を得ることができます。
実技試験では、精米判定・麹判定・きき酒など、お酒の各製造工程における専門的技術が問われます。
酒造に携わる人々
高度な専門性が必要とされる酒造の現場では、酒造りに関するスペシャリストたちが活躍しています。
ここからは、酒蔵で酒造りに携わる人々の呼び名や仕事内容について解説していきます。
蔵元(くらもと)

「蔵元」とは「酒蔵の経営者・当主」を意味します。
経営者1人を指すこともありますが、歴史的に家族経営の多い日本酒の業界では、酒蔵を所有する家の家族を含めて「蔵元」と呼ぶこともあります。
また、酒蔵を持つ酒造会社を指して「蔵元」と言うこともあります。
その場合、製造元の経営者・当主は「蔵元さん」などと呼び分けられるような場面もあります。
杜氏(とうじ)

「杜氏」は酒造りの現場を仕切る最高責任者で、一つの酒蔵に1人だけです。
杜氏は酒造りのすべての工程において酒蔵全体に目を配り、重要な判断や全体の管理を任されます。
また、酒造りの作業だけでなく、酒蔵で働く職人たちの統率をとる役割もあります。
そのため、杜氏には確かな醸造技術や知識に加え、判断力・センス・リーダーシップなども問われ、杜氏の能力が酒の味を左右するとまで言われる重要な役職です。
元々杜氏や蔵人は、農家や漁家が閑散期である秋から春先にかけて季節労働者として酒蔵で働くケースが多かったのですが、以前から後継者不足が懸念されていました。
さらに、年間を通して酒造りを行う四季醸造化が進んでいることや、機械化・IT化によって、近年では社員が杜氏として酒造りを指揮する蔵や、杜氏制度自体をなくす蔵も出てきています。
蔵人(くらびと)

杜氏のもとで酒造りに携わる職人たちを総称して「蔵人」と言います。
蔵人の中でも、担う役割によって役職が決まっており、それぞれの呼び名があります。
蔵人の中でも重要な役割を担うのが「三役」と言われる人たちです。
三役は、杜氏の補佐役として現場で実務レベルの指揮をとる「頭(かしら)」、麹造りの責任者である「大師(だいし)」、酒母造りの責任者である「酛廻り(もとまわり)」からなります。
さらに、三役の下で働く職人たちには、米を洗って蒸す「釜屋(かまや)」や、醪を搾る「船頭(せんどう)」などがいます。
酒蔵に入ると、新人の頃は炊事や雑用を担当する「飯屋(ままや)」から始まり、必要な道具を管理する「道具回し(どうぐまわし)」など、影の仕事をしながら修行を積み、酒造りのいろはを学んでいきます。
日本酒の有名な地域
日本全国で造られている日本酒ですが、日本の中でも特に酒造で有名な地域があります。
国内にはどれくらいの酒造場があり、特にどのような地域で酒造が盛んなのか、国内の酒造事情について解説します。
国内の酒造場の数はどれくらい?

日本国内には1,500を超える日本酒の製造免許場があり、全国各地で日本酒が造られています。
時代とともに酒蔵の数が減っているとは言え、日本酒が日本に深く根づいたお酒だということが見て取れます。
また、日本酒の海外への輸出は年々増加しており、日本酒造りは世界に向けて方向性を広げてきています。
酒造場の多い地域

日本の中でも、特に酒造りが盛んな地域があります。
米と水を原料とする日本酒の製造は、米の産地や良い水が湧き出る地域とも密接に関係しています。
都道府県別に見ると、米どころとして有名な新潟県が最も酒蔵の数が多く、歴史ある老舗の酒蔵も多数存在します。
新潟県に次いで酒蔵が多いのは、酒米を代表する山田錦の名産地である兵庫県や、標高が高く豊かな自然と水脈に恵まれた長野県です。
九州の福岡県や、東北の福島県・山形県、中国地方の広島県などにも多くの酒蔵があり、日本酒造りで有名です。
地域によって日本酒の味に異なる特徴があり、その地域の米や水の特徴を如実に反映します。
例えば、新潟県の日本酒はキレのあるシャープな味わいのものが多く、長野県の日本酒はまろやかでコク深い傾向があります。
また、兵庫県の日本酒はコクとキレをバランスよく兼ね備えた、力強い味わいのものが多くあります。
このように、日本酒には地域性が表れると言えます。
酒蔵見学のできる酒造会社もある

酒造会社の中には、一般の人が見学できる機会や施設を設けているところもあります。
酒蔵見学は、酒造りについて身近に感じたり、酒造りの奥深さを学んだりすることができるのでおすすめです。
その酒蔵で作られる日本酒を試飲できる場合もあり、見る・聞く・味わうという体験が可能です。
例えば、兵庫県にある白鶴酒造資料館は、50年ほど前まで実際に酒蔵として使用されていた建物を改造して開設された資料館で、酒造りの各工程について立体的に展示されています。
試飲のコーナーもあり、日本酒について学び、体験することができます。
伝統ある酒造りの世界を通して「日本のこころ」に触れることができるでしょう。
酒造は伝統とこだわりの結晶
この記事では「酒造」について解説しました。
間違いやすい「酒造」と「酒蔵」の違いについてもご理解いただけたのではないでしょうか。
酒造りは奥が深く、脈々と受け継がれてきた伝統が詰まっています。
現在も、多くの人が携わり、より美味しいお酒を届けるために、日々研究と努力が重ねられています。
白鶴オンラインショップでは、そんな想いのこもった日本酒を多数販売しています。
酒造の世界を想像しながら、実際に日本酒を味わってみてください。